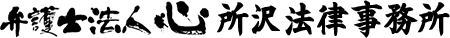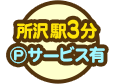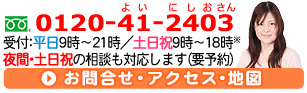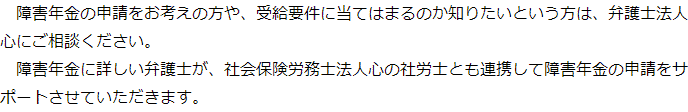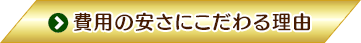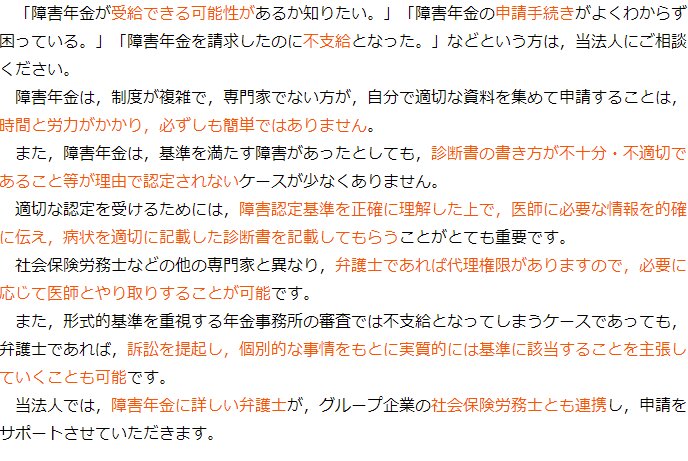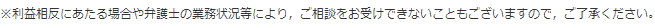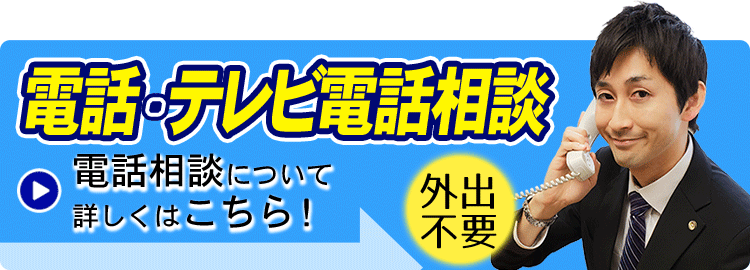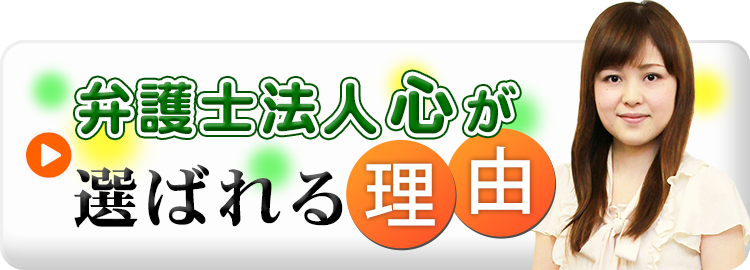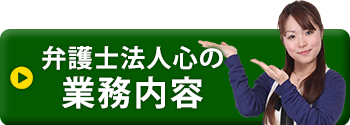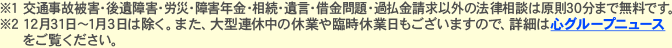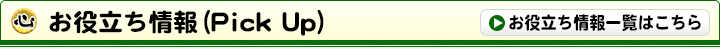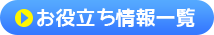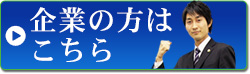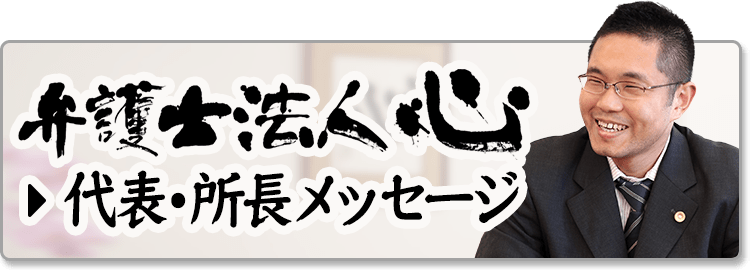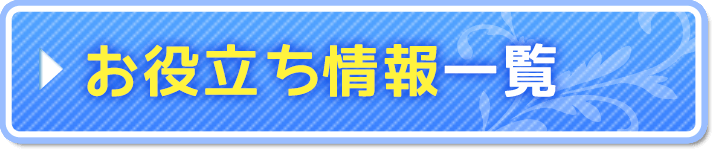障害年金
障害年金を専門家に依頼するとよい理由
1 障害年金受給の可能性が広がる

障害年金をお考えの方には、障害年金制度のことを知らなかったために請求しておらず、初診日が何十年も前であることがあります。
そうすると、カルテが破棄されていることが少なくなく、初診日の立証が困難となり、障害年金の申請を諦めてしまう方もいます。
このような難しい問題に直面した場合に障害年金を専門家に依頼していれば、他の方法を慎重に検討するなどして、初診日の立証につながる方法が見つかることもあり、障害年金の受給の可能性が広がります。
2 診断書に障害の内容が適切に反映されるようサポートを受けられる
障害年金の審査は書類審査であり、医師が作成する診断書の内容は特に重要です。
しかし、診察時間内に日常生活における支障内容等を漏れなく伝えることは困難です。
とりわけ、うつ病などの精神障害がある方は、医師とのコミュニケーションに支障があることが多いです。
この点、障害年金を専門家に依頼すれば、事前に依頼者やご家族からヒアリングして障害の内容等をまとめた補足資料を用意するなどして、障害の内容が診断書に漏れなく反映されるようサポートを受けることも可能です。
3 迅速に請求を進めることができる
障害年金における遡及請求では、障害認定日時点の障害の程度について障害等級に該当すると認められたとしても、請求から過去5年分しか受給できません。
したがって、障害認定日から相当期間経っている場合には迅速に請求をする必要があります。
また、障害認定日時点の障害の程度が障害等級に至らない場合でも、その後に悪化して障害等級に該当するときになったときに請求する事後重症請求では、請求日の翌月分から障害年金を受給できます。
そのため、事後重症請求の場合にも迅速に請求する必要があります。
専門家であれば、ノウハウを生かして迅速に障害年金の手続きを進めることができます。
4 不服申立て手続きに対応することができる
障害等級の認定結果に不服がある場合には、審査請求、再審査請求といった不服申立ての手続きがあります。
しかし、そのような認定結果に至った理由を分析し、その認定が不相当であることを主張立証しなければならず、専門性が高い手続きであるといえます。
この点、専門家であれば安心して任せることができます。
5 弁護士法人心 所沢法律事務所にご相談ください
当法人は、数多くの障害年金の案件を取り扱ってきた実績があります。
障害年金の請求をお考えの場合には、弁護士法人心 所沢法律事務所へお気軽にご連絡ください。
特に障害年金申請を急いだ方がよいケース
1 特に障害年金を急いだ方がよいケース
障害年金は障害認定日以降であれば請求することができ、障害年金の請求が遅くなることで不利益を受けることがあります。
そこで、特に障害年金の請求を急いだ方がよいケースを以下ご紹介します。
2 遡及請求をする場合で、障害認定日から5年以上経過しているケース

障害認定日時点で障害等級に該当していたものの、障害年金の制度を知らなかったなどの理由で、障害年金の請求をしていないことがあります。
この場合、過去に遡って障害認定日時点の障害の程度について審査を求めることができ、この方法を「遡及請求」といいます。
遡及請求により障害等級の認定がされると、障害認定日時点で受給権が発生し、過去分の障害年金ももらうことができます。
しかし、もらえる障害年金は請求前5年分に限られます。
それ以前の分は時効によりもらうことができません。
このように、遡及請求をする場合で、かつ、障害認定日から5年以上経過している場合には、請求が遅くなればなるほど時効によりもらえる分が少なくなるため、請求を急ぐ必要があります。
3 障害認定日から1年経過しそうなケース
障害認定日時点の障害の程度の審査を求める場合、医師に、障害認定日以降3か月以内の症状を診断書に書いてもらう必要があります。
しかし、障害認定日から1年以上経過している場合には、これに加えて、請求前3か月以内の症状が記載された診断書も必要になります。
このように、障害認定日から1年以上経過すると、申請に必要となる診断書が2通となり、取り付けの手間や費用が増大するため、障害認定日から1年経過しそうな場合には急いで申請を進めた方がよいといえます。
4 事後重症請求をするケース
障害認定日時点では障害の等級に該当しないものの、その後症状が悪化して障害等級に該当することになった場合、請求時点の障害の程度の審査を求めることができ、これを「事後重症請求」といいます。
事後重症請求により障害等級の認定がされると、請求日時点で受給権が発生し、請求日が属する月の翌月分から障害年金をもらうことができます。
そのため、請求日が遅くなればなるほど、障害年金をもらえる開始時期は遅くなります。
したがって、事後重症請求を予定している場合には、請求を急ぐ必要があります。
5 弁護士法人心 所沢法律事務所にご相談ください
障害年金は、障害認定日が経過したら迅速かつ適切に準備を進める必要があります。
障害年金でお困りの場合は、お気軽に、所沢の当事務所にご相談ください。
病気やケガが複数ある場合の障害年金
1 病気やケガが複数ある場合の障害認定の方法

病気やケガが2つ以上ある場合、「併合認定」、「総合認定」、「差引認定」といった3種類の認定方法によって、障害認定がなされることになります。
2 併合認定
「併合認定」とは、複数存在する病気やケガについて、それぞれ一つずつ評価した後に、障害の内容を併せて等級を決定する認定方法のことです。
具体例をもとに併合認定の方法を見てみましょう。
<事案>
右手の親指、人差し指、中指、薬指の用を廃し、かつ、両眼の視力が0.1になった
この事案では、まず、「併合判定参考表」という表を用いて、「右手の親指、人差し指、中指、薬指の用廃」と「両眼の視力が0.1」という障害について、それぞれ番号を求めます。
そうすると、「右手の親指、人差し指、中指、薬指の用廃」が7号、「両眼の視力が0.1」が6号に該当することが分かります。
各障害の番号を求めた後は、「併合(加重)認定表」を参照し、各障害の併合番号を求めます。
「併合(加重)認定表」では、「7号」と「6号」の併合番号は「4号」であると定められています。
併合番号を求めたら、その併合番号に対応する障害等級が認定されます。
併合番号が「4号」の場合の障害等級は2級ですので、上記の<事案>での障害等級は2級ということになります。
3 総合認定
病気やケガが複数ある場合でも、①内科的疾患が2つ以上ある場合や、②精神障害が2つ以上ある場合、③傷病は2つ以上であるものの残っている障害が1つ(同一部位)である場合には、「併合認定」の手法を用いることなく、障害の内容に応じて総合的に判断がなされることになります。
これの認定方法を「総合認定」と言います。
総合認定を行う場合は、その認定方法が明確に定まっていない反面、障害の組み合わせがどのようなものでも、等級が繰り上がる可能性があります。
総合認定を行う場合は、その認定方法が明確に定まっていない反面、障害の組み合わせがどのようなものでも、等級が繰り上がる可能性があります。
4 差引認定
「差引認定」とは、複数の病気やケガによって同一部位に障害が生じた場合において後発の障害の程度を認定する際に、後発障害の程度(労働能力減退率)から、以前から存在した障害認定の対象とならない障害(以下、「前発障害」と言います。)の程度(労働能力減退率)を差し引いて認定する方法のことを言います。
なお、「はじめて2級による年金」に該当する場合には、差引認定は行われません。